ある夜、「コーチとして、本当に成長しているのだろうか」と自問自答した夜がありました。銀座コーチングスクールで学び始めて4年。熱心に積み重ねてきた無料相互セッションの数は100回を超えていましたが、心のどこかで違和感がありました。
そして気づいたのです。本当のスキルは練習だけでは決して身につかないことに。
この記事では、コーチング初心者である私が経験した「練習の罠」と「実践の価値」について、あなたと一緒に考えていきたいと思います。なぜ練習より実践の方が圧倒的に効果的なのか、そしてどうすれば限られた練習の時間を最大限に活かせるのか—その答えをお伝えします。
ざっくり見出し
無料相互セッションを100回やって見えた限界
最初は有効だった練習。でも、次第に意味が薄れた
夕暮れの教室で、緊張しながら初めての相互セッションに臨んだ日のことは今でも鮮明に覚えています。銀座コーチングスクールで学び始めた2013年の11月、私は熱意に満ちていました。「とにかく練習あるのみ!」と信じて、コーチ役とクライアント役を交互に務める相互セッションに没頭したのです。
認定コーチになるまでの約半年、Skypeでおよそ40人と50回以上のセッションを実施。毎回セッション後はノートに気づきを書き留め、次回への改善点を見つける日々でした。この時期の練習は間違いなく有意義で、学んだ理論をアウトプットし、確認する場として非常に効果的だったと感じています。
しかし認定後も熱心に練習を続け、1年間でさらに100回近く、60時間以上の相互セッションをこなしました。そして気づいたのです。ある時点から明らかに上達を感じなくなっていたことに。回数を重ねても、スキルの向上が頭打ちになり、時間だけが過ぎていくような感覚でした。
初めの頃は一つひとつのセッションから学びがありましたが、次第に「また同じような展開」「またいつもの質問パターン」と感じることが増えてきたのです。
「やってる感」で満足してしまう心理的な落とし穴
週に何回も相互セッションをこなし、カレンダーが埋まっていく様子を見て「自分は頑張っている」と思っていました。友人に「最近コーチングどう?」と聞かれれば、「今週も5回セッションしたよ!」と胸を張って答える自分がいました。数字で示せる「やってる感」は、とても心地よい錯覚をもたらしてくれたのです。
夜遅くまで続いたセッション後、「今日も一日頑張った」という満足感とともにベッドに横たわる。
しかし冷静になって振り返ると、本当にスキルは向上していたでしょうか?
お互いにお金を払っていない相互セッションでは、残念ながら本気度が足りないことが多かったのです。セッション前に「今日は◯◯を意識してコーチングします!」と決めても、いざ始まると忘れてしまったり、相手からのリクエストも「なんでもいいよ〜」と曖昧だったり。当日のリスケジュールも頻繁に発生し、時間通りに始まらないことも少なくありませんでした。
そして最大の落とし穴は、「100回のセッションをこなした」という事実だけで満足してしまうことでした。数をこなすことが目的となり、質を追求する姿勢が失われていったのです。
心に刻みたいのは、数より質、そして練習より実践の価値です。
なぜ実践の方が圧倒的にスキルが伸びるのか?
本番は緊張感も準備も全く違う
初めての有料クライアントとのセッション前夜、眠れないほどの緊張と興奮を覚えています。何度も資料を見直し、質問リストを用意し、想定されるシナリオを頭の中でシミュレーションしました。これまでの相互セッションとは比較にならないほどの準備時間を費やしたのです。
実際のクライアントを前にしたとき、その緊張感はまったく異なります。セッションの一言一言に責任が伴い、相手の人生や仕事に影響を与える可能性があることを強く意識します。この「重み」こそが、コーチとしての成長を促進する要素なのです。
前回のセッションを何度も振り返り、戦略を練り直し、コーチングの本を読み返す。そうした本気の準備が、自然とスキルアップにつながっていきました。
対照的に練習では、慣れてくると準備もほとんどせず、「とりあえずやってみよう」という姿勢になりがちです。この緊張感と準備の差が、最終的なスキルの大きな差を生み出すのです。
お金が動くと、責任感と集中力が変わる

このセッションは本当に価値があっただろうか・・・?
有料セッション後、この問いが常に頭をよぎりました。クライアントがお金を支払ってくれたことへの感謝と責任を強く感じ、その対価に見合う価値を提供できたかを自問自答する日々。この内省の繰り返しが、コーチとしての成長を加速させたのです。
有料クライアントからの「ありがとう」「視点が変わりました」という言葉には、特別な喜びがあります。それは単なる社交辞令ではなく、提供した価値に対する正直な反応であり、対価を払った人からの評価だからこそ重みがあるのです。
相互セッションでの「ありがとう」と、お金を払ってくれたクライアントからの「ありがとう」。同じ言葉でも、その重みは天と地ほど違います。この違いが、コーチとしての成長曲線を大きく変えるのです。
実際のクライアントは予定通りに反応してくれない

すみません、その質問の意図がよくわかりません

なぜそんなことを聞くんですか?
関係ないと思うのですが…
コーチングを知らない一般の方にセッションすると、想定外の反応の連続です。教科書通りの質問が通用せず、練習で培ったパターンが通用しない現実に直面します。この「想定外」こそが、真のスキル向上のきっかけとなるのです。
こうした困難に直面したとき、本気で解決策を模索するようになります。セッション後にメールでフォローアップしたり、次回のためにより効果的な質問を考えたり、クライアントの特性に合わせたアプローチを研究したり。この試行錯誤のプロセスが、コーチとしての引き出しを増やしていくのです。
一方、練習相手の多くはコーチングを学ぶ仲間であり、質問の意図を汲んで「理想的な」反応をしがちです。質問の真意を理解できなくても「なるほど、深いですね」と返すため、実践で必要な対応力が鍛えられないのです。
実践でぶつかる壁こそが、最高の学びの機会だと気づきました。
練習セッションが効果的でなくなる理由とは?
テーマや目的を共有していない”とりあえずセッション”
SNSで「相互セッション、誰か練習しませんか?」と募集し、「いいですよ〜」と返事をもらい、何となくスケジュールを合わせる。この「とりあえずやる」という気持ちで行われるセッションには、明確な目的が欠けていることが多いのです。
「今日のセッションで何を達成したいですか?」と聞かれても、「特に決めていません」「スキルアップ全般で」といった曖昧な答えしか用意していない状態では、セッション後に何が良かったのか、何を改善すべきかの判断基準もなくなってしまいます。
ある日の相互セッション後、相手から「どうでしたか?」と感想を求められ、私は「良かったです!参考になりました!」と答えました。しかし心の中では「何が良かったのか、何が参考になったのか、具体的に言葉にできない…」という空虚さを感じていました。これは目的意識の欠如から来る現象だったのです。
フィードバックが曖昧だとスキルが磨かれない
コーチングスキル向上において、的確なフィードバックは欠かせません。しかし、多くの相互セッションでは「良かったよ」「すごく参考になった」といった表面的で曖昧な感想しか交換されないことが多いのが現実です。
本当に役立つフィードバックは具体的であるべきです。「この質問はどのように感じましたか?」と尋ねても「良かったです」では、何も学べません。「あの質問で私の考えが一気に深まりました」「ここでもう少し掘り下げてほしかった」といった具体的な指摘があってこそ、次回への明確な改善点が見えてくるのです。
相互セッションで効果的なフィードバックが生まれにくい理由の一つは、お互いの関係性にあります。「批判的に聞こえるかも」「相手を傷つけるかも」という遠慮が働き、本音のフィードバックを避けてしまうのです。
「設定」されたテーマではリアルな練習にならない
最も衝撃的だったのは、練習相手が架空の「設定」を作ってセッションに臨むケースでした。

実は新しい事業を始めたいんですが、親の介護が必要になって時間が取れなくて…
こうした演技のような設定を持ち出されるのは本当に最悪。本人の真の悩みではないため、コーチングの練習としては全く意味がありません。コーチングは表面的な会話ではなく、相手の内面に働きかけるものです。架空のシナリオでは、リアルな反応や感情が得られず、実践での対応力は養われません。
あるセッション中、相手の反応があまりにも薄いので「これは本当にあなたの悩みですか?」と尋ねたところ、「いえ、練習だから設定してみました」という返答。その瞬間、時間の無駄を感じたのを鮮明に覚えています。
コーチングの本質は相手の真実の内面に触れること。演技では決して得られない本物の反応こそが、コーチとしての感性を磨くのです。
効果的な練習にするための3つの条件
練習相手の”選び方”がすべて
効果的な練習のためには、相手選びが何よりも重要です。私の場合、何十人もの相手と練習を重ねましたが、真に有意義だったのは数人との練習だけでした。
理想的な練習相手とは:
- 同じレベルの意識と目標を持っている人
- 遠慮なく率直なフィードバックを伝え合える関係の人
- 継続的に成長を共有できる人
SNSなどで知り合った程度の浅い関係では、心を開いた深いやり取りが難しく、また継続的な成長の共有も困難です。数を追うよりも、信頼できる少数の仲間と深い練習を重ねる方が、圧倒的に効果的です。
「誰とでも練習すれば良い」という考えは捨て、「この人となら本気で成長できる」と感じる相手を慎重に選ぶことが、練習の質を高める第一歩なのです。
「今日の練習のテーマ」を明確に決める
「今日のセッションでは何を練習したいですか?」
この一言から始まるセッションと、ただ漠然と始まるセッションでは、得られる成果に雲泥の差があります。効果的な練習には、明確なテーマ設定が不可欠なのです。
例えば:
- 「今日は質問力を高めたいので、特に掘り下げ質問に集中します」
- 「クライアントの抵抗に対する対応を練習したいので、あえて難しい反応をしてください」
- 「セッション構成の流れを改善したいので、時間配分に注意してください」
このように具体的な目標を共有することで、セッション後のフィードバックも的確になり、確実なスキルアップにつながります。漠然と「コーチングの練習」をするよりも、焦点を絞った練習の方が、圧倒的に効果的なのです。
ある時、「今日は沈黙の活用を練習したい」と決めてセッションしたところ、普段よりも意識的に沈黙を取り入れることができ、相手からも「沈黙の間に考えが整理できた」という具体的なフィードバックを得られました。この経験から、テーマ設定の重要性を実感しました。
「本番を想定した練習」こそ成長につながる
「練習は本番のように、本番は練習のように」
この言葉は、あらゆるプロフェッショナルに通じる真理です。練習であっても、本番と同じ心構えで臨むことが、真の成長につながります。
- セッション前の準備を本番と同じように行う
- 時間厳守を徹底する(開始時間、終了時間)
- 集中力を本番同様に維持する
- セッション後の振り返りも丁寧に行う
これらの姿勢で練習に臨むことで、本番との差を縮め、より実践に近い経験を積むことができます。逆に言えば、本番で緊張せずリラックスして臨めるようになるためには、練習の質を高めることが不可欠なのです。
あるコーチ仲間は、練習でも必ずスーツを着用し、オフィスの会議室を借りて行うという徹底ぶり。最初は大げさだと思いましたが、その姿勢がその人のプロ意識を表しており、実際にクライアントからの評価も高いことに気づきました。
まとめ|練習に満足せず、実践で学びを深めよう
「練習は本番のように、本番は練習のように」
コーチングの道を歩み始めて4年。数多くの相互セッションと実践を通じて、私が到達した結論はシンプルです。
真のスキル向上には、練習と実践のバランスが重要であり、特に実践からこそ得られる学びが大きいということ。練習の段階から本番を意識し、本番ではリラックスして練習の成果を発揮する—このサイクルこそが、プロのコーチへの近道なのです。
「練習をたくさんこなした」という事実に満足するのではなく、「どれだけ成長したか」「どれだけクライアントに価値を提供できるようになったか」という本質的な問いを常に持ち続けることが大切です。
自分の成長のために、あえて実践の場に飛び込もう
最後に、これからコーチングを学ぶあなたへのメッセージです。
安全な練習の場から一歩踏み出し、実践の荒波に身を投じることを恐れないでください。最初は不安や緊張でいっぱいかもしれません。失敗することもあるでしょう。でも、その経験こそが、あなたを真のコーチへと成長させるのです。
コンフォートゾーン(快適領域)から出て、実践の場に飛び込むことこそ、真の成長につながります。練習は基礎を固める場であり、実践こそが真の鍛錬の場なのです。
「十分な準備ができていない」と感じるかもしれませんが、実践を通じてしか学べないことがあります。小さな一歩から始めて、一人でも多くのクライアントと向き合う中で、あなただけの「コーチングの形」を見つけてください。
その先に、クライアントの人生に真の変化をもたらせる、本物のコーチとしての姿があるはずです。
あなたのコーチングの旅が、実りあるものになることを心から願っています。




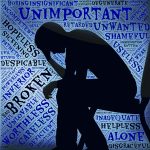

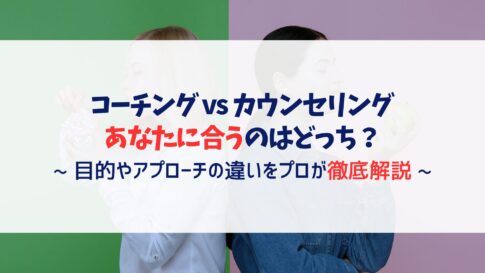



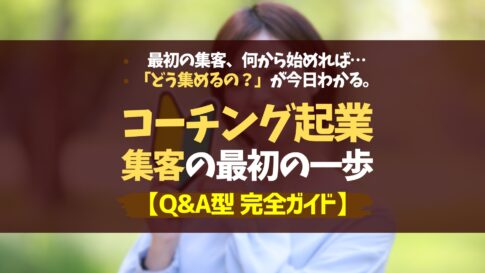
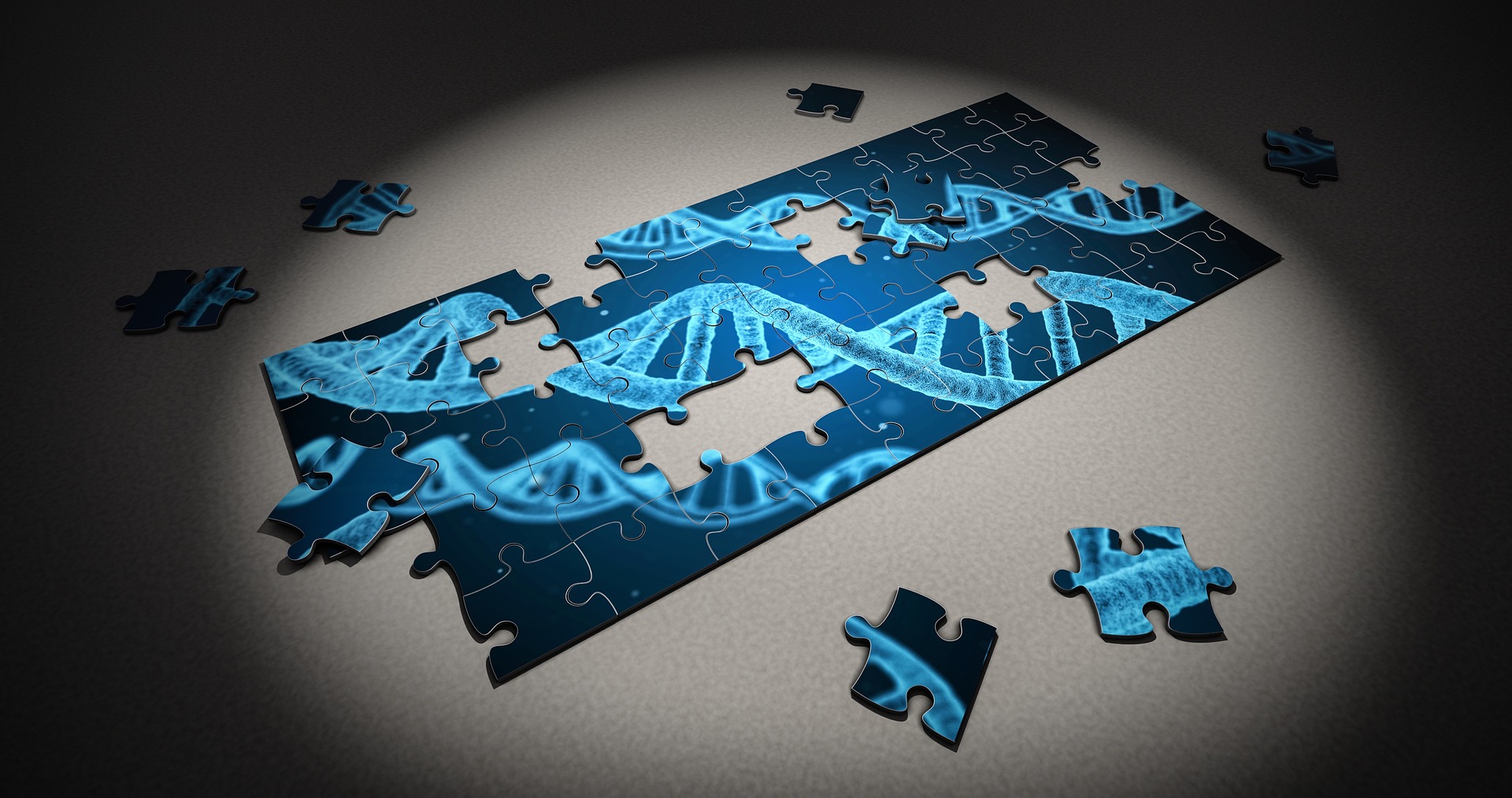

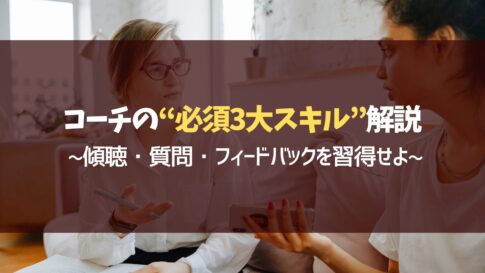
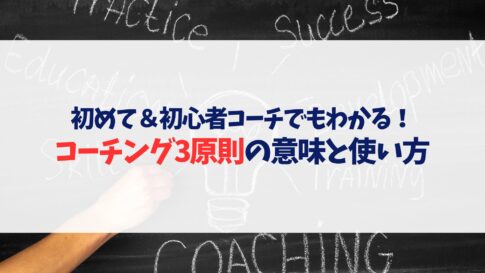
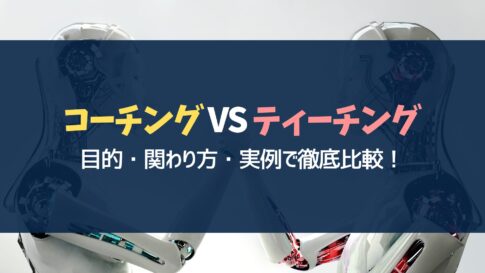
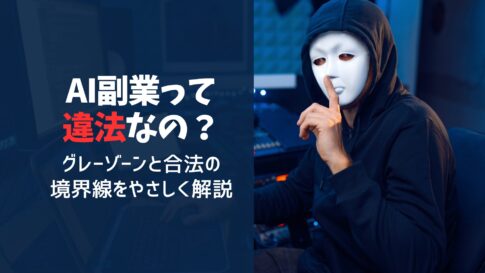

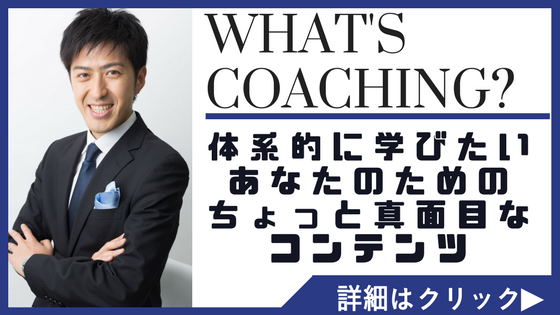
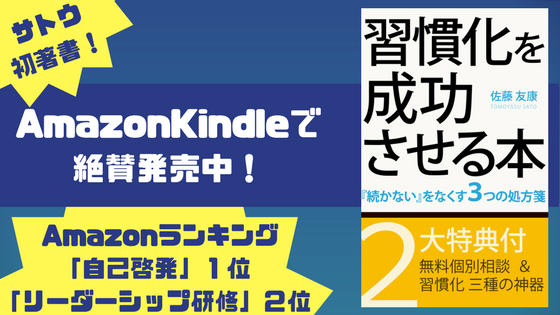

本当にこれで良いのか?
これで上手くなっているのか…?