物があふれる現代社会。あなたの周りにも、使わないけれど「いつか使うかも…」と捨てられないものが溢れていませんか?本記事では、「一日一捨」という片付けの習慣がもたらす驚きの効果と、継続するためのコツをご紹介します。
捨てることは「残す」こと。そして、残ったものを活用して未来につなげること——。この視点が、あなたの部屋と心を同時に整理する鍵になるでしょう。
ざっくり見出し
「一日一捨」を習慣にしたら、片付けがラクになった話
一日一捨とは、その名の通り「毎日必ず何かひとつを捨てる」という習慣です。シンプルなルールですが、続けることで驚くほど生活が変わります。私もあるクライアントから教えてもらい、3ヶ月以上継続しています。
「いつか使う」が溜まっていた過去
起業直後、自宅で仕事をするようになり、「机の上をキレイにする」ことを日課にしていました。集中力を奪う原因になるからです。
しかし、ある時気づいたのです。「毎日のように片付けている」という事実に。
毎日20分も机の整理に費やしていたことに愕然としました。週に換算すると2時間以上、月に10時間以上です。その時間があれば、ブログ記事を5つ書けるし、クライアントのコーチングも10回できる計算になります。
よく考えると、問題の本質は「モノが多すぎる」ことでした。起業して数ヶ月、模索の時期だったため様々なものを試していました。必要なものはどんどん買い足していましたが、不要になったものを捨てる習慣がなかったのです。
片付けの本質は「減らす、減らす、減らす!」
そして「残ったものを整理する」。
モノを一時的に別の場所に移動させるだけでは、真の整理整頓とは言えません。
捨てなければ、新たなものは入りません。そして単に「モノが存在している」だけで、探す手間の増加、注意資源の浪費、目に入ることによる集中力の低下など、様々なデメリットが生じるのです。
一日一捨が続いた”始め方のコツ”
あるクライアントが「一日一捨」という習慣を始めたと聞いた時、「これはいい!」と直感的に思いました。彼は起業家としての大先輩でしたが、その言葉に即座に共感し、私も採用することにしました。
彼が教えてくれた捨てる基準はシンプルでした。

過去どれだけ役に立ったか、ではなく、
未来にどれだけ使うかの観点で評価する
この判断基準が明確だったからこそ、迷うことなく続けられたのです。捨てることに抵抗がある人も、この基準を意識すれば行動しやすくなります。迷うなら捨てた方がいいのです。そうしないと、大切なものがそうでないものに埋もれてしまいます。
捨てることは、残すものを大切にすること
この視点が、習慣を始める強力な動機になりました。
「一日一捨」で得られた4つの効果と変化
一日一捨を3ヶ月続けて感じた、驚くべき効果をご紹介します。単に物理的な変化だけでなく、心理面にも大きなポジティブな影響がありました。
モノが減って、頭もクリアに
一日一捨の最も基本的な効果は、モノが減ることです。当たり前のようですが、実は非常に重要な変化です。
普通に生活しているだけでは、意識的に捨てない限りモノは減りません。
ちょっと考えてみてください。最近、服や本、文房具などを捨てたのはいつですか?明らかな「ゴミ」は捨てやすいですが、それ以外のものは捨てるタイミングがないため、自然と増え続けてしまうのです。
モノが減ると、「時間」も節約できます。探す時間が激減するのです。
物を探す時に20秒以内に見つかりますか?
「探している時間」は何も生み出さない、純粋な無駄です。
また、掃除や整理にかかる時間も減少します。私の場合、机の整理が20分から5分に短縮されました。この時間の積み重ねは、年単位で見ると大きな差になります。
ここ1年使っていないものは、おそらく一生使わないでしょう。
一生使わないものを持ち続ける意味はあるのでしょうか?
「もったいない」から自由になる思考
捨てることへの障壁が下がるのも、大きな効果です。
要らないモノに「No」と言えるようになってきます。これは見方を変えると、過去の自分の選択や価値観を否定することでもあります。
否定というか、価値観のアップグレードという方が適切かもしれません。
「だってこれ、2万円で買ったのに…」という思考は、アップグレードする前の自分を大切にする考え。2万円で買っても、もし現在使っていなければ価値はゼロです。モノは購入した瞬間に中古となり、市場価値が下がります。買った時の金額でモノを評価するのは無意味なのです。
大切なのは、
今の自分がそのモノにどれだけの価値を感じているか
「今の価値観」で測ることです。
捨てる障壁が下がると、プライベートや仕事の基準にも変化が生まれます。時間は有限ですから、本当に必要なもの以外には「No」を言わなければなりません。「より少なく、しかしより良く」というエッセンシャル思考にもつながる大切な考え方です。
迷わず手放せる”決断力”が育つ
無駄なものに囲まれている人は「あれもこれも大事」と考え、本当に大事なものを見失いがちです。会社の全書類に「重要」のハンコを押しているようなものです。
捨てることが習慣になると、何が必要で何が不要かを瞬時に見極める力が身につきます。つまり、決断力が向上するのです。
決断力とは自分の判断軸に従って物事を決定する能力です。一日一捨を通じて、その判断軸がより強固になります。
この決断力は、プライベートだけでなくビジネスにおいても非常に重要です。特に経営者や起業家は「判断すること」が仕事の大きな部分を占めます。毎回の判断に時間をかけていては、スピード感が失われます。
変化の速いこの時代、即断・即決・即行動が求められます。普段から決断力を鍛える習慣を持つことは、ビジネスパーソンにとって大きなアドバンテージとなるでしょう。
自分にとって本当に必要なものが見える
不要なものがなくなり、大切なものだけに囲まれると、心理的な余裕が生まれます。
新しい服や気に入っている服を着ると気分が上がりますよね。逆に「くたびれてきたな」と思う服を着ると、気持ちも下がります。この感情の違いは、日々の生活の質に大きく影響します。
要らないモノを捨てれば、大切なモノ・お気に入りのモノだけが残ります。お気に入りに囲まれている自分は、自信に満ちた状態でいられるのです。
片付けコンサルタントの近藤麻理恵さんも著書「人生がときめく片づけの魔法」でこう述べています。

ときめくものは残す。ときめかないものは捨てる
「ときめく」という表現がしっくりこない人もいるかもしれませんが、要は好きなもの、大事なものを大切にしましょう、ということです。
不要なものに囲まれていると、本当に大事なものを大事に扱えなくなります。一日一捨で、要らないものを少しずつ手放していくことで、本当に価値あるものが見えてくるのです。
片付けのやる気が出ないときの対処法|一日一捨を習慣化するコツ
一日一捨を始めて数週間すると「もう捨てるものがない」と感じるかもしれません。しかし、それでも片付けが中途半端だったり、やる気が下がったりすることがあります。モチベーションを維持して継続するためのポイントをご紹介します。
捨てる”基準”を決めると迷いが消える
捨てられない最大の理由は、捨てる基準があいまいで、その都度迷っているからです。明確な基準を先に決めることで、判断がスムーズになります。
例えば、洋服なら、こんな基準を作ります。
- 1年着ていなかったら捨てる
- 持っていることを忘れていたものは捨てる
- 「7枚」を超えたら捨てる、など枚数を決める
- 迷ったら捨てる
このように基準を決めておけば、都度悩む必要がなくなります。基準に従って「捨てるロボット」になるだけです。
迷うようであれば、友人に捨ててもらうというのも効果的な方法です。他人は客観的に判断できますから、あなたが抱える心理的な抵抗感なしに決断できます。
「残す理由」より「使っているか?」で考える
多くの人は「これを捨てるべきか?」と考えがちですが、発想を逆転させて「これを残す理由は何か?」と問うことで、より明確な判断ができます。
残す理由として有効なのは「現在使っている」「近い将来確実に使う予定がある」といったものです。
逆に、「いつか使うかもしれない」「高かったから」「誰かにもらったから」といった理由は、実は残す十分な理由にはなりません。
「未来にどれだけ使うか」という視点で評価することで、本当に必要なものだけを残せるようになります。過去への執着ではなく、未来への貢献度で判断するのです。
一日一捨は、モノだけじゃない”思考の整理術”だった
一日一捨の習慣は、物理的なモノだけでなく、目に見えない要素にも応用できることに気づきました。
情報・人間関係・感情の断捨離にも効く
モノを捨てる習慣が身につくと、他の領域にも自然と影響していきます:
情報の断捨離: SNSのフォローを整理する、メルマガの購読を見直す、ニュースアプリの通知をオフにするなど、入ってくる情報を選別することで、精神的な余裕が生まれます。
人間関係の断捨離: エネルギーを奪う関係や、成長を妨げる交友関係を見直すことで、より充実した人間関係を築けるようになります。すべての人間関係を大切にしようとするより、深めるべき関係に集中する方が、お互いにとって有益です。
感情の断捨離: 過去の後悔や未来への不安など、不要な感情にとらわれるのをやめることで、現在に集中できるようになります。「今」を生きることの大切さに気づくでしょう。
「捨てる力」は未来を選ぶ力になる
人生は選択の連続です。何かを選ぶということは、必然的に他の何かを選ばないということです。無限の可能性から一つを選び取る勇気が、充実した人生への鍵となります。
一日一捨の習慣は、この「選ぶ力」「選ばない力」を鍛える日々のトレーニングになるのです。モノを選別する単純な行為が、人生の重要な決断にも活きてくるのです。
まとめ|捨てることで、決める力が育つ
片付けられない=決断できない、だった過去
モノを捨てられない人は、モノを大事にしているつもりかもしれませんが、実は逆です。あれもこれも大事というのは、何一つ大事にできていない証拠なのです。
片付けられない状態は、決断できない状態と同義です。「これは必要か?」という小さな判断を先送りにし続けることが、人生の大きな判断も先送りにする習慣につながっていきます。
「決断できる自分」へと変化した実感
一日一捨の習慣を通じて、サトウは「迷わず決められる自分」へと変化していきました。日々の小さな決断を積み重ねることで、大きな決断にも恐れを感じなくなったのです。
本当に必要なものは多くありません。一日一捨を習慣にして、不要なものを手放すことが当たり前になれば、心の余裕も生まれていきます。
あなたの机や引き出し、本当に必要なものだけになっていますか?この記事を読みながら、余計なものが目に入ったなら、今日から一日一捨を始めるチャンスかもしれません。
捨てることは、残すこと。そして、自分の人生を自分で決めること。一日一捨の習慣が、あなたの暮らしと人生に、新たな清々しさをもたらすことを願っています。
一日一捨をすぐにスタートしたいあなたへ
『一日一捨』の記事は、以前よりご好評いただいております。読者の方から、「具体的に、どう捨てればいいの?」と言うことについても質問をいただきました。
記事内でも一部盛り込むとともに、5つの軸をまとめた無料PDFをご用意しました。
限定プレゼント:『一日一捨を習慣にして決断力を高める「5つの捨てる決断の軸」』を無料でダウンロードしてください。
具体的な判断基準と実践のヒントを網羅した内容ですので、ぜひご活用ください。

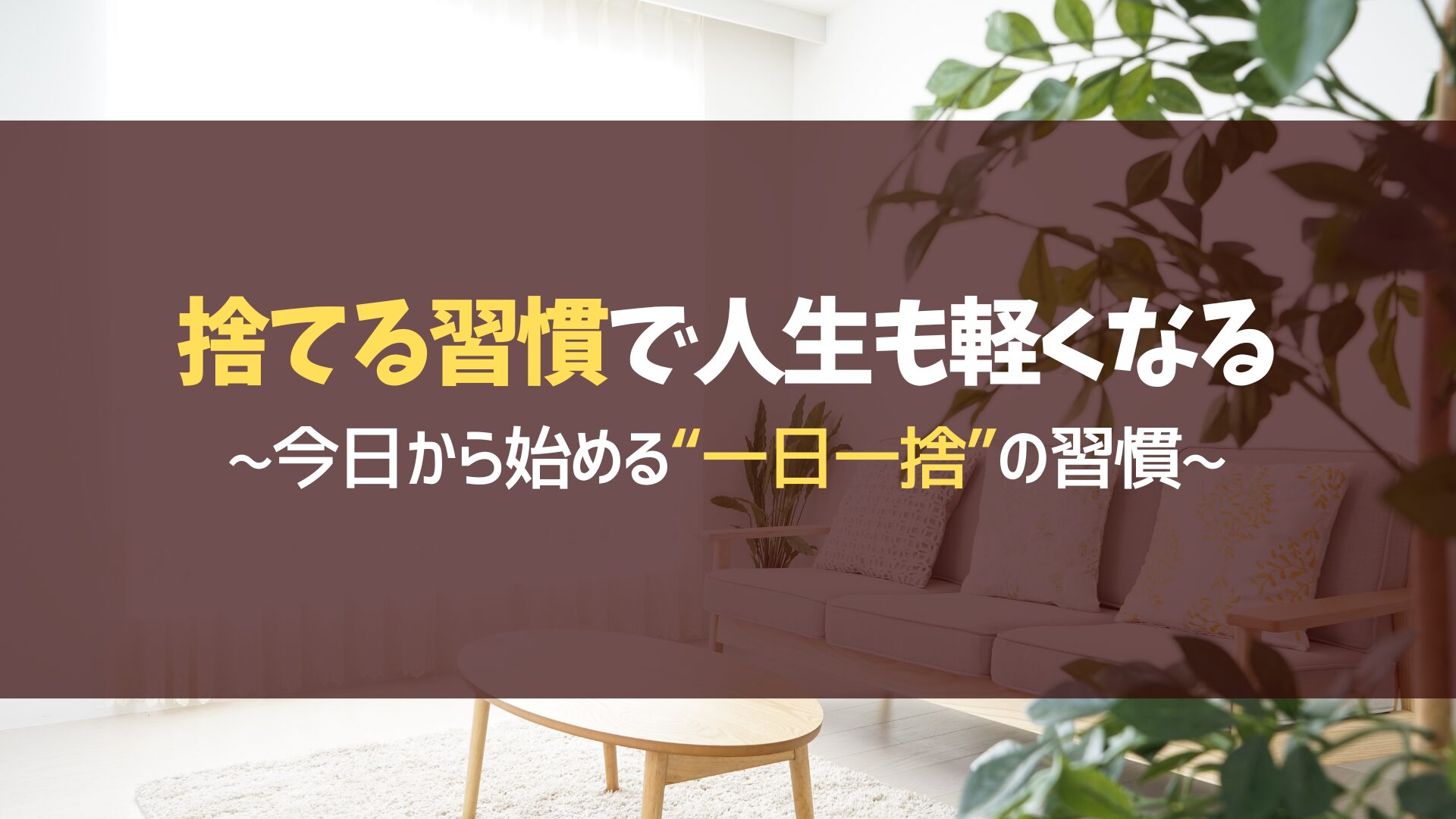

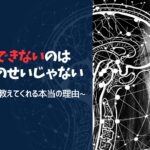
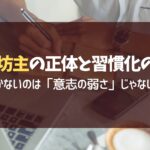
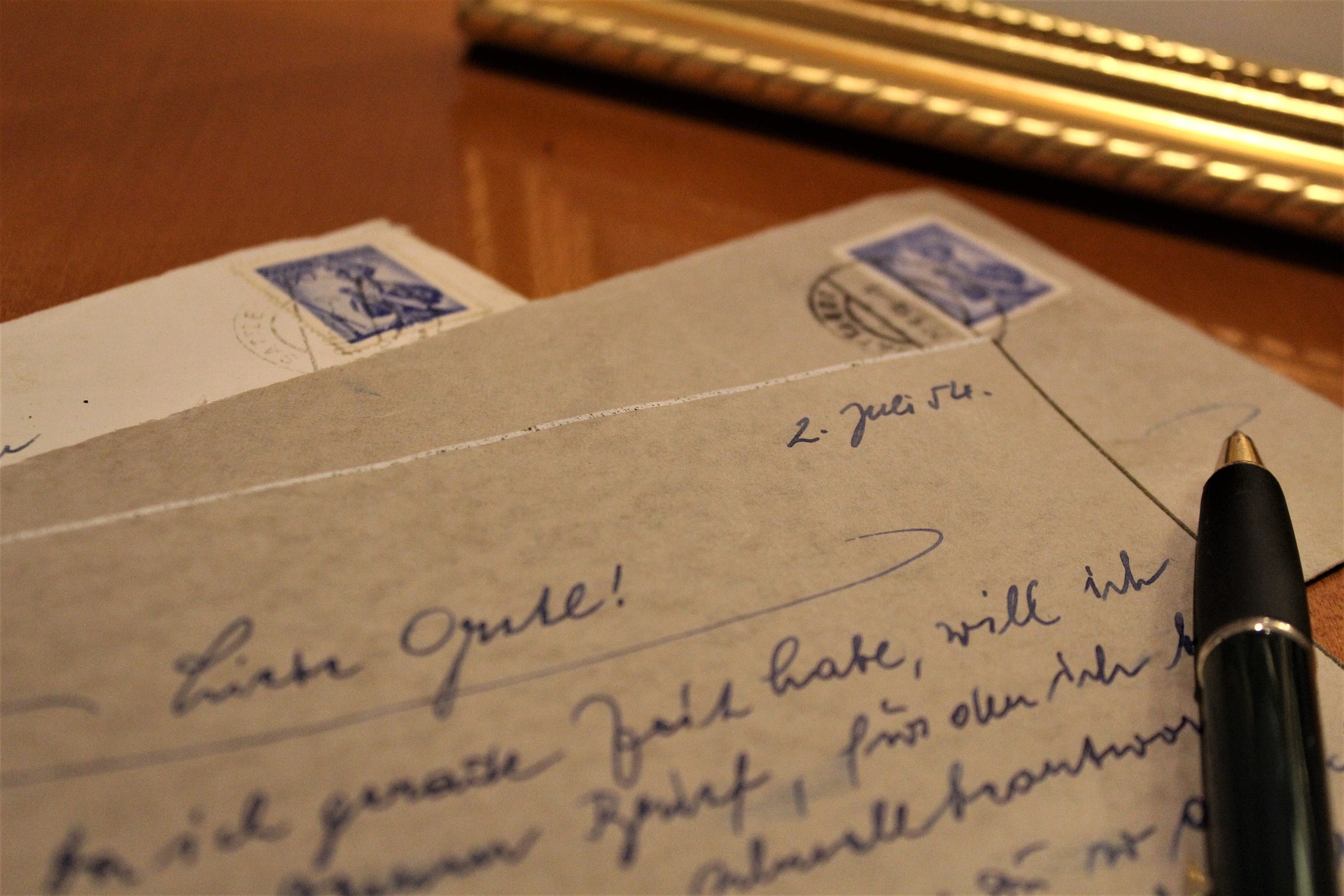

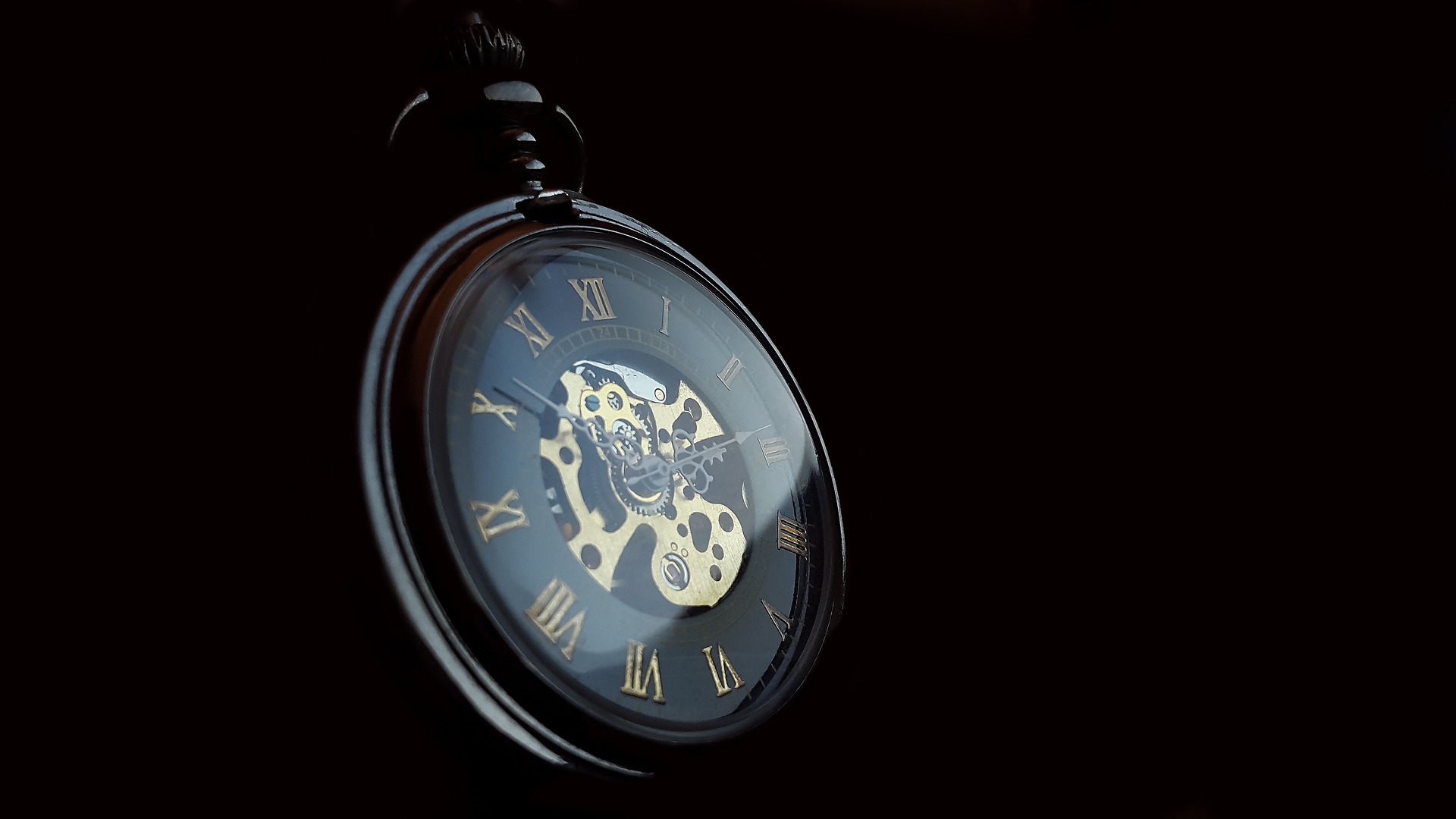



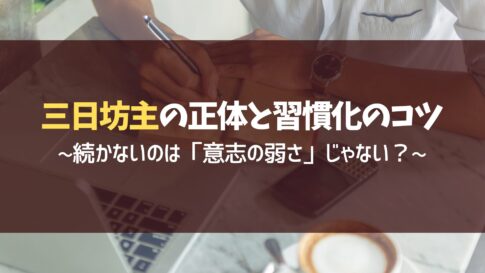

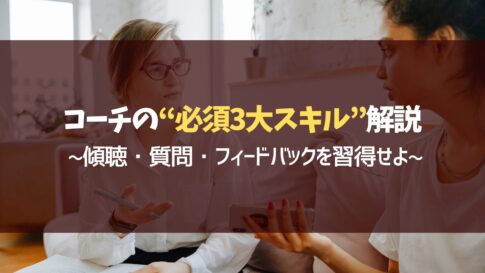
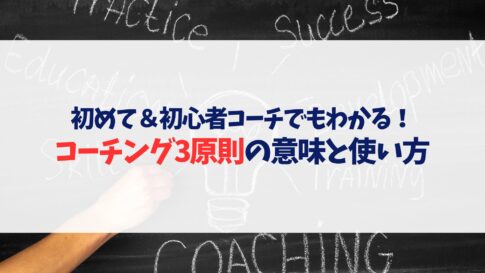
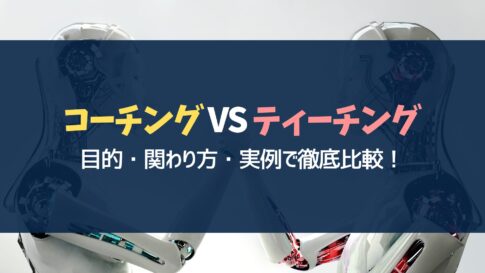
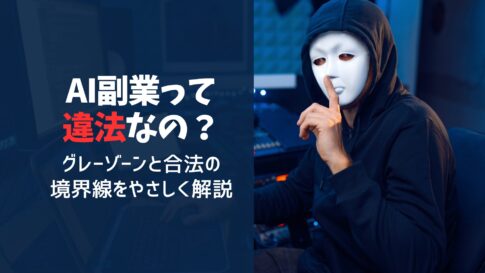

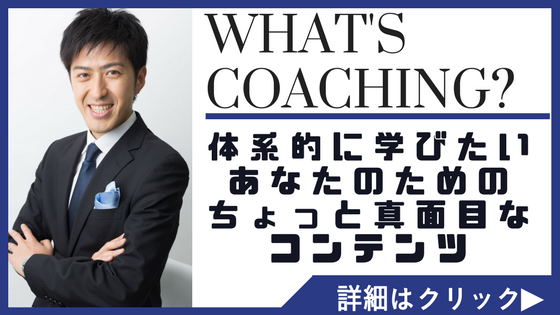
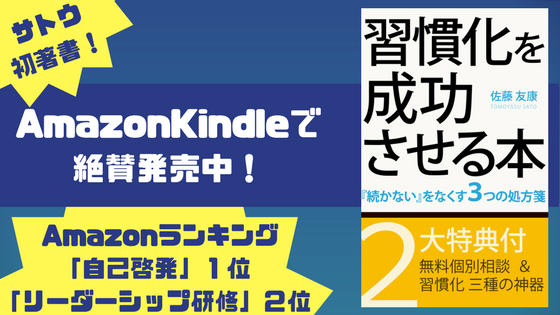

これって、つまり「毎日汚している」ということの裏返しではないか?